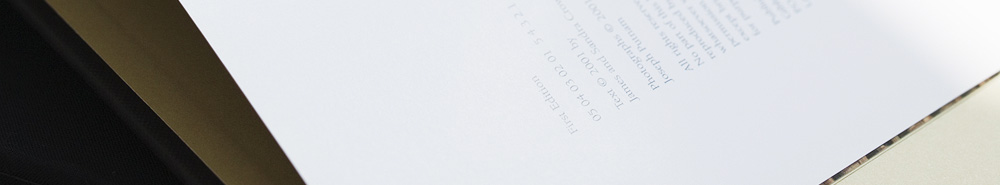- HOME
- クリニックブログ
-
2014.04.15
鯉のぼりを飾ってみました
Category : ブログ
-
2014.04.05
不安には“文脈”がある
Category : ブログ
<名古屋でカウンセリングを重視した心療内科クリニック、船山メンタルクリニックです>
不安は恐怖と違って、“これから起こること”への懸念であり、しかも全く偶発的に起こるものへの懸念は“今どのように行動したらよいか”の葛藤を起こさないので、今の状況に関わる何かが“悪い結果につながりそうだ”という予想を含んでいます。
「顔が赤いから→気が小さい人だと思われる」
「電車だとすぐに降りられないから→発作で倒れると手遅れになる」
「この間も仕事がうまく行かなかったから→今度もだめだろう」
などです。
つまり不安には、条件文で示されるような“文脈”、“仮説”があります。
不安の原動力は、危険から逃れようとする欲求ですが、この気持ちがおかしいと思う必要も是正しようとする必要もないのではないでしょうか?
『不安がいけないものか?』を考えるにあたって、そもそも“不安”という得体の知れないものが自分から独立して存在しているかのような解釈の仕方が間違っているような気がします。
つまり…“不安という症状は存在しない”のかも知れません。
不安の扱いに悩み始めた時…「どのような時に→どうなってしまうと恐れるのか」と文脈を考えることは役に立つかも知れません。
それでも「そうしたら不安がなくなるんですか?」とさらに安心を求めようとしてしまうものです。周囲から“安心を与えてもらえる”ことを求め続けても限界があります。なぜなら不安は“自分の頭の中の懸念”から大きくなるのですから。
-
2014.04.03
不安について
Category : ブログ
<名古屋でカウンセリングを重視した心療内科クリニック、船山メンタルクリニックです>
不安とは何かについて改めて考えてみようと思います。
精神医学の一般的な教科書であるカプラン臨床精神医学テキスト(メディカル・サイエンス・インターナショナル社)には「不安と恐怖との違い」が記載されていて、
「不安(anxiety)は警告を促す信号であり、差し迫った危険を知らせ、人が脅威に対処するための策を講じられるようにする。
恐怖(fear)も同様の警告信号であるが、不安とは区別しなければならない。恐怖は既知の、外界の、はっきりと限定された、あるいは非葛藤的な脅威に対する反応である。」
とあります。
これではどうも日常感覚でわかりにくいので、もうすこし噛み砕いてみると、恐怖とは目の前の脅威に対する主に身体の自動的反応であり、不安とは“脅威が生じる”という危険警報として、実際の危機に先回りして強くなり、危機から逃れるように働くということです。
つまり例えば暴漢に教われて感じるような命の危険などの「恐怖」があることによって、その「恐怖」の取り扱いに人は困らないのであり、恐怖を感じたら直ちに逃げないといけないのです。
しかし不安は“不安に対して困る”という状態になり得ます。つまり、「つまらないことを言ってだめな人だと思われたらどうしよう」「電車に乗っている間に動悸の発作がでて倒れてしまったらどうしよう」など、“これから起こりうること”への懸念は “今どのように行動するか”の葛藤を生むのです。
「人との会話を避けるかどうか」「新幹線に乗らないかどうか」は本人が決めることなのですが、皮肉にも不安によって避けるようになったことは次の場面での不安を強めます。不安は実際に外界に存在する対象に対してではなく、その人の頭の中の懸念が起点となって大きくなっていくので、不安が楽になるための出口がありません。
それでは不安はいけないもの、病的なものなのでしょうか?
この点を次回に検討したいと思います。
-
2014.01.27
開院から1ヶ月になります
Category : ブログ
-
2013.09.30
認知行動療法における“認知の歪み”について
Category : ブログ
認知行動療法と聞いて、皆さんはどのような治療を思い描くでしょう。「歪んだ考えを修正して気持ちを明るくする」というような内容をご覧になった方が多いのではないでしょうか。
ところで、「あなたの考え方が歪んでいる」と言われたとしたらどう思いますか?わかってもらえないような気がしませんか?そもそも歪んでいるというのは“何を基準に歪んでいる”のでしょう?
私は「認知の歪み」という表現が好きではありません。「認知の偏り」と表現した方がよいと思っています。“認知自体が歪んでいる”のではなく“様々な解釈があるはずなのに一つの考えにこだわる”ようになることが患者様のつらさを作り出すからです。つまり、患者様のつらさを作りだす考え方自体が問題ではなく“他の考えが見えていない”ことが問題であるように思います。
では他の考えが見えるためにはどのようにしたらよいでしょう。考えだけを変えようとしても難しいことが多いです。なぜなら患者様の考えは各人の経験に基づいてそれなりに根拠をもっているからです。考え・認知が変化していくためにはそれ相応の根拠となるような経験が必要です。そのために行動を介して認知を変化させられるといいのではないかと考えています。
![]()
![]()
- ・2024年11月
- ・2024年9月
- ・2024年7月
- ・2024年5月
- ・2023年12月
- ・2023年7月
- ・2023年2月
- ・2022年12月
- ・2022年8月
- ・2022年7月
- ・2021年12月
- ・2021年11月
- ・2021年7月
- ・2021年3月
- ・2020年12月
- ・2020年7月
- ・2019年12月
- ・2019年10月
- ・2019年8月
- ・2019年4月
- ・2018年12月
- ・2018年10月
- ・2018年8月
- ・2018年4月
- ・2018年3月
- ・2017年12月
- ・2017年8月
- ・2016年12月
- ・2016年8月
- ・2016年1月
- ・2015年12月
- ・2015年7月
- ・2015年6月
- ・2015年4月
- ・2015年1月
- ・2014年12月
- ・2014年8月
- ・2014年4月
- ・2014年1月
- ・2013年12月
- ・2013年9月